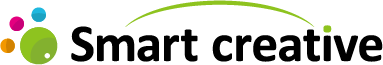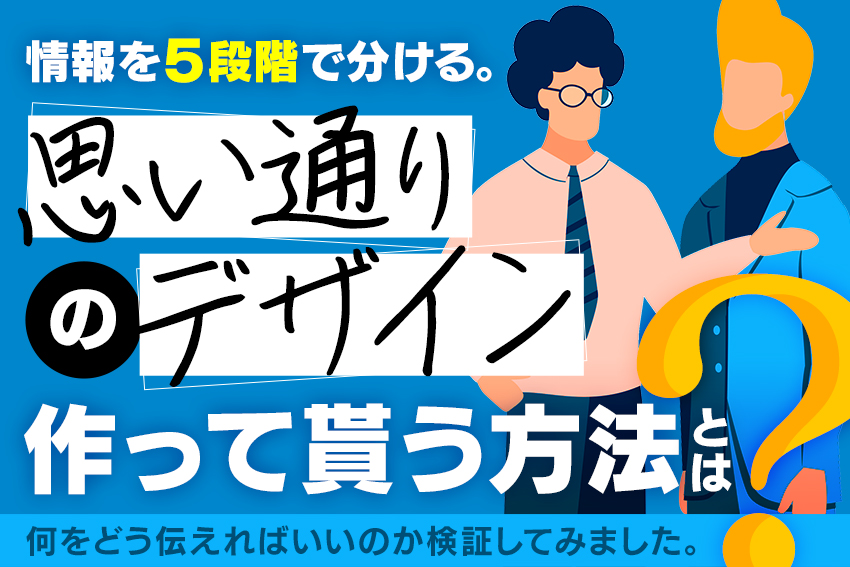こんにちは!デザイン部責任者の平野です。
これまで「【第1弾】ヘブンネットのデザイナーに「おまかせ」で依頼してみたら、どんなのができるの?」で同じ依頼であってもデザイナーによって提案されるデザインには差異があること、そして「【第2弾】思い通りのデザインを作ってもらうにはどうすればいい?」にて提供する情報によっては望んでいるものと違う場合がある事を検証してきました。
そこで今回はそもそも依頼をするにあたって「何をどう考えて何を伝えるべきなのか」と、提出されたデザインのイメージ等が違う場合「何をチェックすればいいのか」をまとめてみました。
人によっては「もの凄くどうでもよくて、ありえないくらい長い」内容なので、デザインにこだわりや、興味のある方のみ読んでみてください!
依頼編
最低限の情報提供
最低限制作に必要なものは
・制作サイズ(00px×00px)
・記載情報
となります。これさえあれば最低限デザインの構築は可能です。ただあくまで最低限の情報なので、余程相性のいいデザイナーを見つけない限りは「【第1弾】ヘブンネットのデザイナーに「おまかせ」で依頼してみたら、どんなのができるの?」と同様に仕上がりにムラができてしまったり「なんか違う…」となってしまう可能性が高い事をご理解ください。
ですので繰り返しますが下記以降は「デザインにこだわりたい」という場合ご覧ください。
初めて依頼をする/依頼に慣れていない場合
そもそもデザイナーでない方がデザインを明確に言語化して伝えることは、ほぼ不可能であると考えています。なぜならそれはデザイナーでも難しく、うまくできない人たちがたくさんいるからです。なので、初めて依頼される方や、依頼に慣れていない方はそのまま「慣れていない」「何をどう伝えればいいかわからない」という旨をお伝えいただけるのが一番だと思います。
そうすればその背景を理解して、デザイナー側の提案の内容や提案の際のデザインの説明も変わってきますし、「相談したい」とお伝えいただければ制作前の段階で「こういうのはいかがですか?」と打ち合わせも可能ですので、ご納得いただける可能性は高くなるかと思われます。
コンセプトを設定する。
基本的にデザインを依頼するときには「どんな見た目にするか?」を考えがちなのですが、個人的には依頼の背景、つまりなぜデザインが必要なのかが重要な前提条件になると思っています。それをコンセプトとして定義しておくことで依頼者とデザイナーの中での共通認識になり、より適切なデザインが上がってくる事が期待できます。
ちなみに広告における”コンセプト”とは「狙い」という言葉に置き換える事ができると思っています。
つまりこの広告(バナー)で
①誰に
②どんな情報を
③どんな印象で伝えて
④どんな反応を引き出したいのか
この狙いを言語化して明確に設定してきます。
このコンセプトによっては広告の狙い・目的が変わってくるので適切なデザインが変わる可能性があるのです。
例えば家電量販店の中に掲示する「テレビの販促ポスター」の広告制作の依頼があったと仮定しての例を出していきます。
①誰に
先程のテレビの販促ポスターの例でもし
A.「ゲームや映画好きの若い世代の方」
B.「テレビが古くなって買い替えを検討している高齢の方」
のようにターゲットが変われば必要なデザインが変わってくるのは想像しやすいですね。
弊社媒体の場合は明確で「ヘブンネット→男性ユーザー」「ガールズヘブン→女性求職者」ですね。しかし内容によってはこれに条件が足されていき、より解像度が高くピンポイントなターゲッティングになっていきます。
(例)”20代”で未経験”の求職者/”出張客”のヘブンネットユーザー など
②どんな情報を伝えるべきか
どちらもテレビの値段や機能・スペックなど基本情報の記載情報が必要なのは間違いないでしょうが、何をメインにするのかが優先順位が変わります。
【Aの場合】———————-
フレームレート・画質・音質など機能性
【Bの場合】———————-
画面サイズ・値段・スタッフまでお気軽にお声がけください。などの接客サービス
などのように変わるかもしれません。
ここで注意したいのは、依頼者が”伝えたい事”と、狙っているの”ターゲットの知りたいだろう事”をできるだけ重ねる必要があるという事です。弊社媒体でも同様に例えば求人で「30代の経験者女性」に対して訴求する内容と、「20代前半の未経験女性」には訴求すべき内容が変わってくるのは想像しやすいですよね。
③どんな印象で伝えるべきか
【Aの場合】———————-
「ゲーミング・スタイリッシュ・綺麗・シック」などデザイン性の高い印象
【Bの場合】———————-
「誠実・堅実」といった印象
などのような違いをつけてもいいかもしれません。
ここが普段「どんなデザインにしよう?」と考えられている部分ですね。例のように適切な「印象」はその他の要素によって変わります。ここでもターゲットに沿った印象が必要で、デザイナー・依頼者の「個人的に好きなデザイン」に偏ったものにならないようにするのが重要なポイントです。
④どんな反応を引き出すか
これも例えば「パンフレットを手に取ってもらいたい」「スタッフに声をかけてほしい」などによって文言等が変わるかもしれませんね。バナーの場合はほとんどがリンク先へ遷移させる。が必要な反応になりますね。
ただ例えばヘブンのスマホスライドにイベントを告知するバナーを掲載するにしても、その後のユーザーの導線をどのようにするかによっても変わります。イベントページに飛ばすなら情報はバナー内で完結する必要がなく、ユーザーを引き付けるような仕掛けに重きをおくべきでしょうし、予約に飛ばすならある程度情報が完結している必要があるでしょうし、狙いの反応によっても色々変わりますね。
このように実はコンセプトが変わることによって適したデザインが根底から変わってしまう場合があります。なので依頼の際にとりあえずイメージサンプルをつけていればOKという事でもないのです。そのサンプルが実は狙いに適していない可能性があるからです。ただ、普段のすべてのバナーをここまで細かく設定して考えていく事は難しいとは思いますので、こういった考え方もあるんだと頭の隅にでも置いておくだけで構いません。それだけでも十分に「広告の機能性」に着目して、広告を見る目が変わるかと思います。
欲しいバナーのイメージのある/なしで発注方法は変わる
イメージがある場合
明確なイメージがある場合は「【第2弾】思い通りのデザインを作ってもらうにはどうすればいい?」で検証した通りイメージに近づけていくために必要に応じて「記載情報・優先順位・雰囲気・サンプル・ラフ」などを細かく指定していけばいいと思います。
ただそこまで上記の検証ほど明確な完成イメージがない事がほとんだと思います。こういった雰囲気にしたいというものはあるからサンプルを提供したけれど、ほとんどトレースしたようなものが上がってきた。という経験はありませんか?
こんな雰囲気で。という意味合いであって「これを咀嚼してよりよいものを提案してほかった…」という声を聞いたこともあります。
これは1点だけサンプルを渡すと、デザイナーは上記の検証時のような「明確な完成イメージ」だと認識してしまい、制作時の”縛り”になってしまうからなのです。なのでそういう場合は複数枚の似たようなサンプルを渡しておくか、「あくまでサンプルです」的な旨を伝えるのがよいと思います。
イメージがない場合
イメージがない場合はデザイナーの考える力を大いに利用しましょう。大きなこだわりがない場合はシンプルに「おまかせ」でも構いません。イメージは浮かばないけれど、いいものにしたい。といった場合は上記で記載したコンセプトを設定したり、もしくはデザイナーと打ち合わせて一緒にコンセプト設定をしていき、依頼者とデザイナーで思考のすり合わせを行う方がよいと思います。
デザイナーの理解が深まれば、より納得度の高いデザインを提供してもらえる割合が増えると思っています。これらは感覚的なセンスというよりも経験則に基づいた”想像力”や”引き出しの多さ””対応力”になるので社歴の長いデザイナーを選ぶ基準にしてもいいかもしれませんね。
修正編
何をチェックするべきなのか?
「なんか違う…」と思っていても、何をどう直せばいいのか、言語化するのは非常に難しいですよね。前述のようにサンプルを完成イメージだと理解してトレースしたような印象のようなものだった場合、修正で「色を変えてみてほしい」と伝えると本当に色しか変わらない…という事もあります。
私は弊社のグループ会社全員のデザイナーの技術点数をつけている4人の責任者のうちの1人なのですが、大まかに下記7項目をチェックして点数をつけています。(もっと細かく見ている部分もありますが…)よければフィードバックの際にチェックしてみてください。
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 広告の機能性 | ・情報に間違いや混乱を生む表現がないか ・必要な情報が最低限伝わっているか ・効率よく伝わりやすくなっているか |
| コピー | ・言い回しに無駄はないか ・適切な文字量か ・語呂感などコンセプトに沿った表現か ・ファンタジー、ポエムに振り切ってはいないか |
| 配色 | ・配色の印象が合っているか ・明度・彩度(トーン)がそろっているか |
| タイポグラフィ(文字) | ・フォントと印象が合っている ・フォントの種類を多用して散らかっていないか ・伝達の必要のある情報は可読性が高いか |
| レイアウトやリズム | ・読む、見る順番に迷わないか ・必要な順に情報が取得できるか ・広告内に適切な変化があり見飽きることなく終着できるか |
| 写真・素材 | ・魅力的な位置で写真が使用できているか ・不要な箇所が写りこんでいないか ・切り抜き後のエッジは綺麗にできているか ・色調はバナー全体と調和が取れているか ・使用素材のテンションが合っているか |
| グラフィック | ・伝達内容に適したイメージになっているか ・望んだイメージになっているか |
前途した「コンセプト」が達成できているかどうかを、上記内容をチェックして判断する。といった形になります。
広告の機能性
■情報に間違いや混乱を生む表現がないか
→間違った情報・誤植、ややこしい記載の仕方をしていないか。
■必要な情報が最低限伝わっているか
→狙いにはよりますが、肝心の伝えたいことが全く分からない。といったことのない状態。
■効率よく伝わりやすくなっているか
→例えば「割引実施中」ではなく「最大0000円OFF!!」みたいに、割引がよりお得に感じるように、効率的に伝わりやすくなっているかです。
コピー
■言い回しに無駄はないか
→同じ言葉が重複して使用されていたり、分かりにくい言い回しになっていないか。
例)———————-
メインキャッチ:夏SALE開催中!
サブキャッチ:①夏服最大00%OFF!夏服買うなら今!②夏休みに夏を目一杯楽しもう!
上記の例で言うと極端ですが「夏」が何度も重複しています。それは何度も重複しなくても1回で伝わるでしょうし、夏っぽいビジュアルを作れば十分に伝わります。
■適切な文字量か
→動きのあるスライドバナーのような数秒で流れてしまう箇所や、面積の小さいバナー(スマホで見ることを思うと手のひらサイズ以下)になってくると、表現に使える面積が小さい分、省略できるところは省略して上記のような無駄な言い回しは避けたいですし、量が多くなるほど1つの情報のサイズはより小さくなっていくので、伝達しないといけない情報は精査・取捨選択が必要ですね。
■語呂感などコンセプトに沿った表現か
→例えば高級感の表現をしているけれどコピーの末に「♡」「!!」などイメージと合わないコピーがある場合もあります。ひらがな・カタカナ・漢字・英語など様々な表現が日本の広告ではできてしまうので、コンセプトに沿った表現を心掛けた方が効果的です。
■ファンタジー・ポエムに振り切ってはいないか
→例えば「S級」という言葉があったりしますが、これだけで情報を完結しないほうがいいと思っています。それはユーザーは「なぜS級なのか?」の中身が知りたいからです。例えば何かしらのランキングが高いのかもしれませんし、スタイルが凄くいいのかもしれません。ともかくユーザーの感じる「なぜ?」を解消する必要があり、その解消の部分こそが客観的に「良さ」を伝えるポイントになるからです。
抽象的な表現や具体性の少ない謳い文句がダメなわけではなく、使用した場合は具体的な情報(サブキャッチなど)で補完する。がセットになっている方が効果的ですね。
配色
■配色の印象が合っているか
→例えば、高級感と伝えたのに「赤・黄」でスーパーのチラシのようになってしまっている。みたいな事がないか、与えたい印象に対して適切な色の選定ができているか。
■明度・彩度(トーン)がそろっているか
→一部要素だけ発色が違ったりすると、違和感という差異に変わってしまいます。色の数が多くなるほどに統一感を持たせた調整が難しくなっていき、色数が少ないほど統一感は増すもののメリハリがつきにくくなります。こちらのバランスをトーンを守って行う必要があります。
タイポグラフィ
タイポグラフィとは文字を読みやすくしたり、造形的な加工をする技法・分野の事を指します。
■フォントと印象が合っている
→フォントの選定が与えたい印象に適切な選定になっているか。
ただし高級感だからといって明朝体しか使わない。などの極端な選定は避けた方がよいかと思います。逆に単調になり、メリハリがなくなってしまう可能性があるためです。
■フォントの種類を多用して散らかっていないか
→とはいえあまりに多数のフォントを使用すると散らかった、まとまりのない印象になってしまう可能性が高いのでフォントの種類の数にも注意した方がよいかと思われます。
■伝達の必要のある情報は可読性が高いか
→字と字の間の空き幅や、文章の行の間の空き幅など、読みやすく処理が施されているかです。日本語は縦にも横にも読める特殊な言語ですので、字間・行間のバランスを取り違えると、途端に読みづらくなってしまうものなのです。
レイアウトやリズム
■読む、見る順番に迷わないか
→前途しましたが、縦読みも横読みは字間・行間だけでなく、要素同士の空間のマージン(幅)を適切に取る事でも見やすく・読みやすくすることが可能です。「【おまかせ依頼】田中幹大 編」でも説明をしましたが、WEBにおいては基本的に視線はZ型に流れていくのでどこに情報を配置するかはとても重要です。
■必要な順に情報が取得できるか
→Z型ではない視線の誘導も可能で、一番目立つ要素を右側に配置すれば見る順にはZ以外の変動が起こります。どの順に見せるにしても、最終ユーザーの導線を別ページへ導くために必要な情報を分かりやすい順に取得させる必要があるのです。
■広告内に適切な変化があり見飽きることなく終着できるか
→リズムという表現が正しいかは分かりませんが、ただ文字を打っただけにならないよう適切に変化・差をつける必要があります。例えば日付の曜日が●の中に入っていたり、料金表記にしても「分」「円」が小さかったり、時間を円で囲って金額は外に出す。など、1つの要素でも、いちいちデザインを凝らすことができるのです。そういった適切なデザイン要素の足し引きも必要ですね。
写真・素材
■魅力的な位置で写真が使用できているか
→仮に巨乳推しの女性の全身写真が提供された際にある程度バストアップでトリミングすることが推奨されることは容易に想定できますね。例えばもっと追及すると、少し頭頂部を画角から切るように配置したりすると上部に抜け感が無くなり視線はバナー下部に落ちていきます。すると胸に視線が集まりやすくなったりします。このようにトリミングの位置や角度によって、自然と視線誘導を行うことも可能です。
■不要な箇所が写りこんでいないか
→上記の全身写真の例で言うと胸から下は特に表示する必要のない箇所になります。例えばスタイルの良さをアピールするには全身が必要ですが、アピールする箇所によっては必要のない省くべき箇所が出てくる可能性があります。
■切り抜き後のエッジは綺麗にできているか
→写真等を切り抜いた際に、カクカクしてハサミで切ったようになっていたり、最近だとAIが切り抜いてくれたりもありますが、人の手による切り抜きよりは精度がまだ悪く、輪郭(エッジ)がぼやけていたり、ピクセルが粗く、ジャギジャギになっていないかもチェックポイントです。誤解を恐れず言うなら被写体は全て”商品”なので、綺麗に魅力的に扱う。というのは広告にとって基本的なポイントになるのです。
とはいえ写真の状態によっては、そもそも綺麗に切り抜くのが不可能な場合もあります。(輪郭が背景と同化している・写真サイズが小さい等)
■色調はバナー全体と調和が取れているか
→写真を撮影した際のライティングや色味の雰囲気が、やりたいデザインや世界観に適した状態であることは稀ですので、色調・明度・コントラストなどを調整して全体で一体感のある調整を施す必要があります。
■使用素材のテンションが合っているか
→写真だけでなく、素材集のアイテムによっても同様の事が言えます。同じ素材集であればテンションやテイストは統一感がありますが、別の素材集を扱う場合はアイテムごとにトーンやテンションが違う可能性があります。一見して分かる部分ではないのですが、こういった細部にも適切な処理を施せるデザイナーは仕事が細かく、いいデザイナーであると言えると思います。
グラフィック
■伝達内容に適したイメージになっているか
→ホラー映画のポスターが怖さや不気味さを感じるように、子供向けのおもちゃのパッケージがカラフルだったりキラキラ、可愛くできているように、コンセプト、狙いに沿ったイメージがなされているか。
■望んだイメージになっているか
→依頼したイメージと相違がないか。もし仮に「おまかせ」で依頼した場合には「第1弾」「第2弾」の記事の検証の通り「イメージと違う」のは当然であるので、その辺りはご理解ください。
まとめ
長かったですね。何でもそうですが深掘りすると長くなってしまいますね。
色々書きましたが、これらが必ずしも”広告の正解”でないのが難しいところで、これらに則っていないけれど圧倒的に印象に残っているようなものであったり、感覚的に「かっこいい!」みたいなものも沢山ありますよね。
ただそれらを狙って作るのは難しいものです。
なのでこの記事の内容は”打率を上げる”ために色々理論立ててみたにすぎないものだとご理解ください。
ただ、いかなる広告も共通しているのは依頼者がいてデザイナーがいるという関係です。
反響の出せるいい広告を作るためにも、デザイナーとのコミュニケーションを重要視してみるのも手かもしれません。
弊社の制作サービスはデザイナーを指名する事が可能なので、よきパートナーをぜひ探してみてください。
それでは!